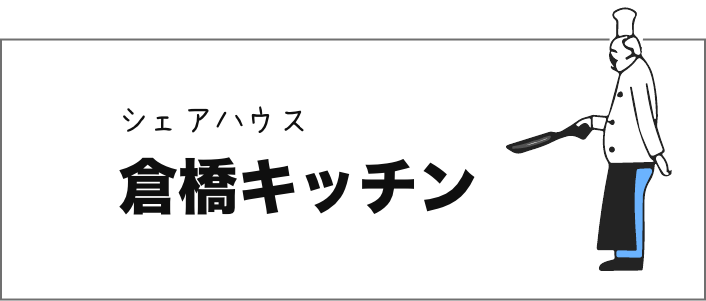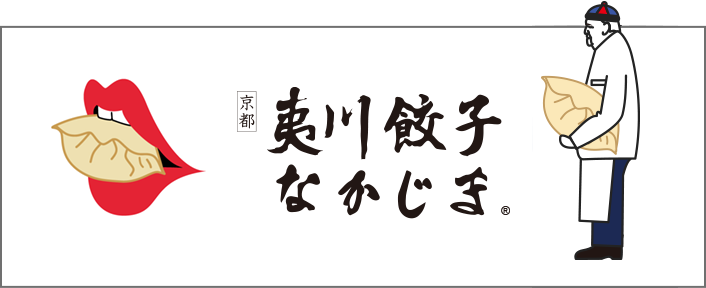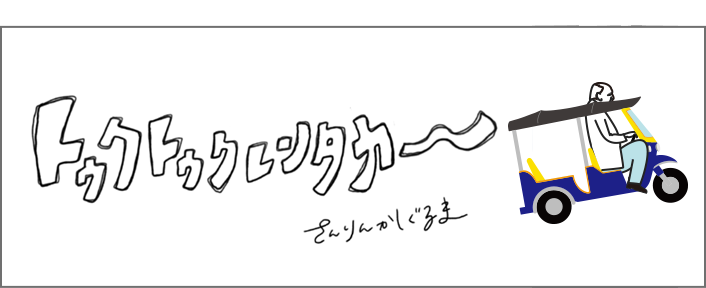作家にとって家は住まいであると同時に職場である。
つまりとても特別な場所。
生涯において、最もかけがえのない場所とも言える。
なるべく人に干渉されないことを生きがいとし、
夜帰る道中にも静逸平穏の喜びを感じる様な、
四十路を目前にした、少し癖のある男の辿りついた結末は。。。
頂緑館
リフォームが完成し、早々に引っ越しする事に。新しい住処は、玄関入ってすぐの廊下が和室になっている。聞くところによると、改装前の趣ある和室の名残を残したかったからだそうで。確かに畳の廊下なんてものは珍しく。拘りの強い彼の美意識をくすぐる。
和室の廊下の先には、透明ガラスの大きな建具の向こうに書斎室が広がる。出来る限り天井が高く取られていて、大きな窓から見える景色は、小高い場所にあるために、街中の様な「隣の民家の壁」と言ったものはなく、目の前には、より開放感を感じられる空間が一面に広がっている。
さらに元々あった半地下部分に本棚を設置し、開放感がありつつも篭れる書斎も作られている。北向きの窓から優しく差し込む光に、端っこに置いてある椅子の上で三角座りし、目を細める彼。
ここでなら、書けるかもしれない―――。

2階にはキッチンともう一部屋が設けられていた。床暖房が設備されていて、細長い窓からは庭の木々がまるで絵画の様に映り込む。きっと四季折々の景色を堪能できるのであろう。また、キッチンのデザインもシンプルで飾りすぎず、大判のタイルと小窓から見える眺めも含め、程よく溶け合っている。新しいのに、まるでレトロな印象を受ける。そしてそれがまた、彼の好みでもある。

書斎部分の天井のデザインや、各部屋に設置された古建具、玄関土間の石など、端々に改装前のデザインをそのまま活用し融合させているので、新しい筈なのに何処か懐かしい空気感が伝わってくる。彼は剃り上げた頭を何度も何度も撫でた。どうやら気分が高揚した時につい出るクセらしい。
トイレや風呂場は、なかなか贅沢な間取りになっている。何ならここにも本棚を置けるじゃないか。と、彼の口元から思わず笑みが溢れるほどの広さだ。以前の手狭な部屋から一転。おそらく彼は、無意識にこの時を待っていたのかもしれない。

昼は丘の裏手にある小学校から子供達の元気な声がうっすらと心地よく、林のざわめきと鳥の鳴き声に混ざり聞こえてくる。最高の自然環境音をBGMにして読書に励む。窓が大きく注ぎ込む自然光が本を読むにはちょうど良い灯りになる。ここに決めて良かったと彼は再び本に目を落とす。
細長く続く石階段もまた、風情のある佇まいの一部である。彼にとってこの不便さは、むしろ愛おしく感じる序章に過ぎない。つまりそれは、己のみぞ知る開放感抜群の隠れ家的書斎室なのだ。

荷物整理さながら、下界へと降りる仙人の様な面持ちで、昼食を食べに早めに家を出る。
先日見つけたお気に入りの定食屋「祭り」は、ランチ時は恐ろしく混んでいる為、開店と同時ぐらいの心構えが必要だ。石階段をゆっくりと降り、木漏れ日が反射する地面を見つめながら、ふと、自分が亡き後は私設図書館として開放してもいいかもしれない。と漠然とした思いが、彼の中から湧いてきた。顔をあげ振り返り、新しい我が住処を遠目で眺める。
その時は、そうだな。―――頂緑館とでも名付けようか。
【Fin】